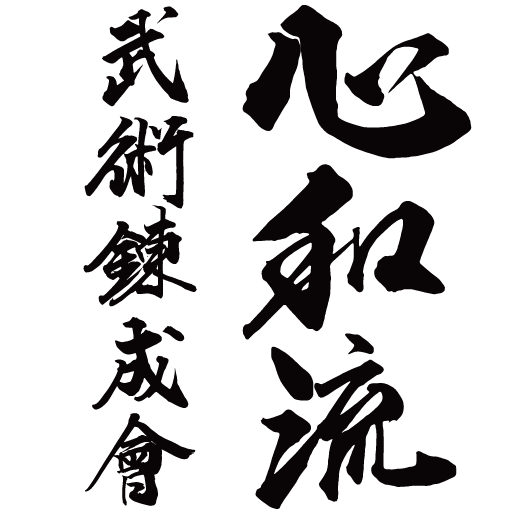なぜ当流は『武道』ではなく『武術』なのか、疑問に思っている会員の方も多いと思うので、『武道』と『武術』についてお話ししたいと思います。
『武道』の成り立ち
『武道』『古武道』という言葉は、古くから使われている言葉のように思われていますが、現代の意味で『武道』が使われるようになったのは、思いのほか最近の事になります。
始まりは明治28年(1895年)、内務省と警察が中心となって『大日本武徳会』が発足したところからになります。
大日本武徳会は小松宮彰仁親王陸軍大将を総裁に頂き、武術の鍛錬を通じて国民の士気を振興することを目的に設立された公的な武術研究機関です。
この武徳会で行われた剣術・撃剣稽古のうち、竹刀と防具を使う防具稽古の事を『剣道』と呼ぶようになりました。
明治44年(1911年)には中等学校の『体操』科目の一部として『剣道』が採用され、大正8年(1919年)には、大日本武徳会武術専門学校の校長、西久保弘道氏が中心となり『剣術』を『剣道』、『柔術』を『柔道』、『武術』を『武道』と定めた事により、現在に続く『武道』の概念が生まれました。
――――
なお、現在武道等で使われる『段級位制度』は江戸時代に棋聖 本因坊道策が囲碁において導入し、囲碁将棋で使われていたものを、明治時代に嘉納治五郎氏が講道館柔道を創設した際に導入したものになります。閑話休題
――――
なぜ『武術』を『武道』の名称に改称したのかは諸説あります。
日本武道館の見解によると『武道は、武士道の伝統に由来する我が国で体系化された武技の修錬による心技一如の運動文化』(日本武道会WEBサイトより引用)とありますので、本稿では『武士道由来説』を紹介したいと思います。
歴史を遡る事1905年、極東の田舎の小さな島国である日本が、当時ユーラシア最強の国家であったロシア帝国を打ち破るという大事件が発生し、世界中が驚愕しました。
そんな日露戦争前夜1899年、5千円札でおなじみの新渡戸稲造氏が「BUSHIDO The Soul of Japan 」を執筆します。
当時、西洋諸国から見た日本の一般的なイメージは神を信仰しない未開の野蛮な民族というような状態でしたが、「BUSHIDO The Soul of Japan 」では新渡戸氏の流暢な英文によって、日本には、西洋の騎士道に並ぶ武士道という倫理規範がある事が紹介されました。
「BUSHIDO The Soul of Japan 」は西欧諸国人にとって、日清戦争・日露戦争で勝利した日本という国がいかなる民族であるかを解き明かす本であり、オリエンタリズム趣味とも相まって、かのセオドア・ルーズベルト米大統領をも魅了し、世界各国の言語に翻訳される世界的なベストセラーになり、明治32年(1900年)には日本国内に「BUSHIDO The Soul of Japan 」が輸入され、遅れて明治41年(1908年)には翻訳版『武士道』が発売されました。
当時は日清・日露戦争の戦勝に湧き高まる国民のナショナリズム感情の中、新渡戸稲造氏だけでなく、国内でも多くの軍人・論客によって武士道論が展開され、武士道は国内外に一大ムーブメントを巻き起こした概念でした。
武士道ブームによって武士に憧れた人々が、文明開化以来忘れられていた剣術や柔術、弓術に関心を持つのは当然で、国内の武術人口も増加しました。
明治28年(1895年)に発足した「大日本武徳会」はそのような時代背景の中、武術を通じた『武士道』の教育をもって忠君愛国の士を養成しようという発想から作られました。
ナショナリズムの高まり、国民の武士道と武術への関心の高まり、そして大日本武徳会という大きな受け皿の存在によって武術愛好家は加速的に増加、明治42年(1909年)には大日本武徳会が財団法人化、その時点でさえ会員数151万人、資産181万円の巨大組織でしたが。その後も会員は増え続け日中戦争の昭和13年(1938年)には会員数300万人を突破しました。
『武士道』に対する憧れと、それを利用する為政者、そういった社会構図は、大正8年(1919年)に『武術』を、『武士道』の略称『武道』へと改めさせました。
時は既に銃の時代、一部の幹部等帯刀本分者以外は軍刀も持たず『戦技』としては剣道より銃剣術に重きが置かれましたが、武道教育の現場では『戦闘技術』よりむしろ『心身の鍛錬』『精神』に重きを置くことで、軍人に対する精神教育や、青少年教育・国民の士気高揚に有用なものとして学校教育に取り入れられていきました。
武徳会の運営する武術専門学校(後に武道専門学校に改称)の卒業生には、『武道』『国語』『漢文』科目の中等学校教員無試験検定が認められ、武道専門学校の卒業生は日本中の中等学校で『武道』を通じて『武士道』の精神を説くことになります。
その後は皆様ご承知の通り、1945年に我が国の『武士道』は無残極まる大敗北を喫し、GHQによる『武道禁止令』によって大日本武徳会は解散させられる事になります。
GHQの命令によって剣道だけではなく、あらゆる武道の稽古は禁止され、多くの日本刀が没収、海中投棄或いは戦利品として国外に持ち去られ、残った日本刀も美術品としてのみ存在を認められる事になりました。
特に剣道に対する風当たりは強く、GHQの上部組織である連合国極東委員会は「日本教育制度改革に関する政策」において、「剣道のような好戦的精神を助長する古典的スポーツもすべて廃止されなければならない。体育はもはや“精神教育”に結びつけられるべきではない」と決定しました。
目の敵にされた剣道は徹底的に規制され、規制を逃れる形でフェンシング競技を参考にして考案された「しない競技」という仮の姿でのみ存在が許されました。
その後、多くの武道家が武道の復活を嘆願した結果、1952年サンフランシスコ講和条約締結と共に武道も解禁され、1952年10月には全日本剣道連盟が発足しました。
講和条約により形式的には主権を回復したとはいえ、当然戦勝国の影響は強く残っており、剣道復活にあたり時の文部科学大臣は保健体育審議会に諮問し、審議会からは剣道復活にあたって4つの条件が示されたそうです。
① スポーツの一種目としての性格を明らかにすること。
② 学生生徒の心身発育にふさわしい競技方法と内容を考えること。
③ 青少年間に広く普及すること。
④ 全日本剣道連盟が,スポーツ団体として組織され民主的に運営されること。
全日本剣道連盟はこの条件を受け入れ、翌年の1953年に 「社会体育としての剣道の取扱について」(文社体第214号)が通知され、『剣道』は完全に戦技から切り離され、新しい体育スポーツとして再出発を果たすことになるのです。
――――――
剣道を中心に見てきましたが、戦後に再開・発展した多くの武道が「平和のための武道」を標榜してきたのは、元々の流派の教えもあると思いますが、武道を守り存続させるための建前として「戦闘技術」であってはならなかった、そうせざるを得なかったという敗戦国としての事情、苦肉の策でもあります。
これが現代我々が目にする『武道』成立の激動の歴史になります。
本来戦技であった武道が敗戦によって失われしまった事は悲しい事ですが、GHQから押し付けられた苛烈な命令に耐え、日本刀が武器ではなく美術品・文化財として延命できたように、戦闘のための技術ではなく心を鍛え平和を愛する純粋スポーツとして『武道』が継承され、今では広く『BUDO~THE MARTIAL WAYS OF JAPAN~』として世界の人々に愛好されるに至った事は、我が国の文化の保護に極めて大きな価値があり、奇策をもって占領軍の目を欺き、武道・武術を守り抜いた先人には心より敬意を払いたいと思います。
武術と武士道は分離して考えるべき事
さて、前段では武道=武士道起源説をご紹介いたしましたが、それでは『武道』の由来である『武士道』とはなんでしょうか?
これも定義は曖昧で、新渡戸稲造氏が創作する前にも、1860年に山岡鉄舟氏が『武士道』を執筆しており、中世江戸時代には「武士道と云ふは、死ぬ事と見付けたり」で有名な山本常朝氏の『葉隠』があり、より前の鎌倉時代には御恩と奉公等の武士の処世術、武士の思想としての武士道に類する概念がありました。
時代によって考え方も色々ありますが、現在最もイメージされるいわゆる『武士道』は江戸時代徳川幕府の儒教的要素を含むものと、それを模倣した明治以降の武士道でしょう。
江戸時代初期に山鹿素行ら儒学者によって作られた『士道論』は『武士のあるべき姿』を説明したものでした。
つまりそれは徳川幕府における軍人官僚を統制するための戒律であり、士道は徳川幕府の治世で長く活用されました。(江戸時代当時は武士道より士道と言われるのが一般的)
特に江戸中期以降、士道において実質的に重視されるのは、武士が為政者にとってコントロール可能かどうかであり、実際に敵に打ち勝つための技術ではありません。
建前上は武士たるもの「治にいて乱を忘れず」とされていたとしても、実質的には天下泰平の世に戦の技術は不要であり、重要だったのは大義名分と建前、礼節と階級を重んじる役人としての処世術です。
鎌倉から戦国時代に発展した『武士の思想』としての武士道は、江戸時代に入って為政者が軍人官僚機構を統治するための武士道に変化したのです。
一方で『武術』は単純に戦闘のための手段という意味でありそれ以上でもそれ以下でもありません。
重要なのは徹底的に合理的である事で、徹頭徹尾、敵に打ち勝つための技術でなければ意味がありません。また、武術は武士だけのものではなく町人百姓だろうと身に着けられます。
天下泰平、徳川時代であれば『武士道』は社会を維持する有効な手段でした、明治維新後、日清日露戦争時代であれば兵士の命がけの斬り込みと気合で何とか勝てたのかもしれません、しかし兵器が高度化した太平洋戦争では、技術の伴わない統治のための精神論としての『武士道』は、圧倒的物量の近代軍と原爆というシンプルな武術の前に敗れ去ることになったのです。
―――――
ひるがえって、現代を生きる我々にも同じ事が言えるのではないでしょうか。
現代日本社会は、あらゆる企業、団体、組織が官僚化されたおり、その中で雇われて働くサラリーマンはさながら現代の武士です。
現代の武士にも、会社や組織の為に滅私奉公で働くという武士道があります。
戦前の武士道が天皇と国家のための滅私奉公であれば、現代の滅私奉公は会社の利益のための滅私奉公です。
世の中が順調に成長し発展していく天下泰平な高度経済成長期であれば、官僚機構はうまく機能し『現代版武士道』も機能してきたのかもしれません。
コンピューターが発展途上だった平成初期であれば、残業と根性の滅私奉公で何とかなったのかもしれません。
しかしIT技術が高度化した現代ではもはや、そのような精神論的武士道では勝つことが出来ません。
要するところ、我が国は先の大戦末期と同じ過ちを繰り返している最中なのです。
今の我が国に必要なものは『武術』です。経済戦争という現在の状況で言えば『IT技術』です。(PCやインターネットは成り立ちは軍事技術なので武術そのものと言えます。)
太平洋戦争、兵器の進化で精神論が通用しなくなったように、IT技術の進化によって根性論も滅私奉公も通用しなくなります。
地方自治体も、企業も、個人も「お国頼み」ではジリ貧になるだけです。一人一人が強くなり、技術を蓄え、自分の力で生きていけなければ国は強くなりません。
今の日本社会には一人一人が自分の力で戦い生き残る術『武術』が必要です。
――――――
太平洋戦争末期、最後の最後、連合国軍に囲まれ本土決戦が現実のものとなりつつある時、大本営もようやく『武士道』の限界に気が付き、たどり着いた結論が『国民一人一人の武術』でした。
それは物資不足のため、竹槍や棍棒、投石機に弓矢、鉄パイプで作ったお粗末な銃、火炎瓶と瀬戸物の手りゅう弾、徒手空拳をもって、上陸してくる完全武装の敵と戦えという悲惨なものでしたが、その時に初めて全ての日本国民が自分の国の未来を『お上』や『軍』『出征する若者』任せではなく、『我が事』として考えなくてはならなくなった瞬間でした。
老若男女を問わず全国で国民義勇隊が編成され、全国紙には国民抗戦必携というゲリラ戦闘マニュアルが掲載されました、町々で竹槍や斧、鎌、鳶口等による白兵戦が訓練され、弓道部の弓には爆薬が括り付けられ、剣道家は真剣を持ち巻き藁を切る一撃必殺の訓練を行いました。
一億総玉砕を覚悟し、最後の一人になるまで日本国は負けない、そう信じ武術を訓練していた人々の耳に、玉音放送がどう聞こえたのかは察するに余りあります。
そして、敗戦の後、焼け野原となった日本国を復興したものは、国が用意した『武士道』などではなく、『一人一人の武術』つまり国民一人一人が自分で戦い、必死で生き残るための努力と覚悟でした。
社会や組織に我が身の安全を守られて漫然と生きている人間と、自分の力で戦い生きる決意をした人間、どちらが強い人間であるかは、比べるまでもありません。それは矢や弾丸が飛び交う戦国時代だけではなく、敗戦の日でも、今日でも変わらない人間の生き方と死に方の原則です。
当流の稽古はあくまでも拳や刀の使い方という意味での武術です。
世界トップレベルの警察力と治安を誇るわが国で、そうしたアナクロな武術が物理的に身を守る手段として役に立つことはほとんど無いでしょう。
しかし、一方で毎年数万もの人々が自らの命を絶つこの現代日本社会は、武術稽古が想定する戦場より遥かに過酷で危険なのかもしれません。
『稽古』とは『古きを稽る(考える)』という意味です。武術の稽古を通じて養われる武術的思考・徹底した合理的思考は、江戸以前、戦国時代の『武士の思想』に通じるものであり、苛烈を極める現代社会、そして、これからより厳しくなる世界的な経済戦争の中での『生き方』に応用できるものがあると考えます。
そして『武術』を身に着けた上で改めて『武士道』を学ぶ事で、誰かに押し付けられた『傀儡のための武士道』ではない『自分の武士道』『自分の武道』を見つけることも出来るでしょう。
――――――
以上、当流が『武術』を標榜する理由です。当流が指導するのはあくまでも『術』だけです。
本稿の内容も当流の歴史解釈の説明であり、強要するものではありません。歴史や思想には誰かの意図や思惑が含まれていたり、往々にして意図しない誤りが含まれているものです。そのようなものに左右されず『道』は自分の頭で考えて、自分の体で体験して自分で見つけてください、それは自分の力で見つけなければ何の価値もありません。
会員諸氏の武術稽古が実り多いものになる事を切に願います。